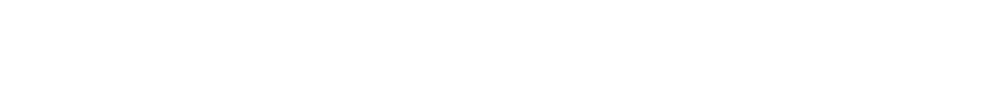ジャン=リュック・ゴダール、ヨーロッパを二分する自殺幇助に手を染める
火曜日に91歳で亡くなったジャン=リュック・ゴダール監督は、スイスで自殺幇助を受けていました。欧州では全会一致の賛成を得られない行為。そして特にフランスでは、この話題が世間で再浮上しています。
ジャン=リュック・ゴダール監督は、スイスで合法的に行われている自殺幇助に頼りました。「医療報告書の条件によれば、複数の無力な病状の後でした」と、遺族の顧問であるパトリック・ジャンヌレは説明します。
スイスでは、映画監督が使用したような自殺幇助は認められていますが、特に規制はありません。スイスの刑法では、自殺を幇助する者は「利己的な動機」に基づいてはならないと規定されている。この概念は、イグジットやディグニタスといったスイスのいくつかの団体が、死を望む人々に法的支援を提供する上で、十分に曖昧なままとなっているのである。
一方、利益を得るために自殺を煽った場合は、5年の懲役または罰金に処せられます。関係者の識別能力が損なわれていないこと。外部からの影響は一切認めない。そして、候補者は自分自身に毒を投与することを余儀なくされる。
「老後の任意解約」に向けて?
昨年、スイスでは1,400人近くが付き添い死を遂げています。この数字は約20年間、右肩上がりで推移しています。
監督側としては、複数の「障害病理」を抱えていたのだ。死ぬわけではなく、「ただ疲れているだけ」だったのだ。家族の顧問の発言を信じるなら、ジャン=リュック・ゴダールは確かに自殺幇助の対象であったことになる。すでに2014年の時点で、この処置に賛成していることを隠していなかった。スイスのラジオ・テレビ局RTSの取材に、彼は主治医にそのことを尋ねたという。
8年後、医師は彼に自殺幇助の効果があると判断したようだ。しかし、スイスの法律はまだ明確ではありません。尊厳死の権利を主張する人たちの中には、病気でない人にもこの慣習を拡大し、一種の自発的な老後の中断を求める人たちもいます。
また、自殺幇助協会などの関係者は、流される可能性を恐れている。スイスで、夫と一緒に死にたいという健康な80歳の女性を助けた医師が訴追された。
自殺幇助、欧州で膨大な議論
このフランス系スイス人映画監督の訃報は、フランス国立諮問倫理委員会(CCNE)が火曜日に発表した意見を受け、フランスのニュースで議論が再燃したところである。この意見書の報告者の一人であるAlain Claeysは、この文書の中で、「積極的な死の援助を倫理的に適用する方法は、妥協できないと思われる一定の厳しい条件の下で存在する」と説明している。
この厳しい条件の中で、委員会が特に強調しているのは、自殺幇助の対象は、身体的・精神的苦痛をもたらす重篤な難病で、難治性かつ生命予後が中期的に約束されている成人とすることである。もうひとつのおすすめは、本人の意思をサポートすることです。つまり、「この要請は、しっかりとした情報提供、不変のもの、意欲的なものであることを保証することが必要であろう」ということです。
また、フランス全土での緩和ケアの実施について、受け入れがたい状況も指摘されました。この意見に難色を示すCCNEのメンバー8人によると、この問題によって、適切な緩和ケアがないために、死への幇助に走る人が出てくる可能性があるとのことである。
「この意見は、まずレオネッティ法がよりよく知られ、よりよく適用されなければならないという事実を主張するものである。CCNE会長のJean-François Delfraissy博士は、「フランスでは、緩和ケアのための追加的な資源が不可欠です」と述べています。
レオネッティ法では対応しきれない状況も一定数存在します。特に、数週間から数ヶ月という中期的な終末期を迎える患者さんです。このことは、私たちの死は私たちのものなのか、そして、ある状況下で死の援助を受けることを望む条件を、私たちは決めることができるのか、という問いを提起しているのです。CCNEは、このような複雑なテーマを進展させるために、このような非常に難しい問題をテーブルに載せているのです。
しかし、CCNEの意見は一致していない。サン=ドニ病院の緩和ケアと集中治療の心理学者で、病院の地域倫理委員会の委員長を務めるサラ・ピアッツァは、レオネッティ法は十分だと考えているが、介護者や患者にはあまりによく知られていないことが多いと考えている。
“終末期 “というと、いわゆる “治療的延命 “のイメージが強いですが、実は “治療的延命 “ではなく、”治療的延命 “なのです。しかし、レオネッティ法は、このような延命措置から患者を守るためのものです。治療を拒否することもできるし、たとえ死につながる治療であっても、痛みや苦しみを和らげるための治療に付き添うこともできるのです」とピアッツァさんは言います。
“医療への不平等なアクセス “という問題があるのです。
サラ・ピアッツァによると、最大の問題は、医療へのアクセスである。
今日、緩和ケアへのアクセスは、すべての人に可能というわけではありません。そしてそこには、医療へのアクセスの不平等という問題がある。フランスには、緩和ケア病棟がない診療科が26あります。緩和ケアの恩恵を受けるべき患者さんの3分の2は、緩和ケアを受けられないと言われています。だから、現実に今のところ人々がそれを利用できないのに、あるケア案が不適切だと認定するのは、問題を逆さまにするようなものです。
倫理委員会のメンバーも、この問題の複雑さを認識した上で、国民的議論の絶対的必要性を主張した。月曜日、共和国大統領は、2023年末までの「法的枠組み」の変更の可能性を視野に入れ、3月に結論を出す終末期に関する市民協議の開始を発表しました。彼は、議会での結果も国民投票も否定していない。
ヨーロッパで終末期医療の問題が議論されているのはフランスだけではありません。このテーマは、ベルギーやオランダなど他の国でも定期的に議論されており、近年では法律が改正され、非常に管理された方法で安楽死ができるようになっています。
ゴダールとスイス、その長い歴史
忘れられがちですが、ジャン=リュック・ゴダールはフランス人であるだけではありません。また、スイス人である。彼の両親は、彼が生まれるずっと前、第一次世界大戦のさなかにレマン湖のほとりに定住していた。そして、彼自身は第二次世界大戦中にスイスに定住することを選んだ。
映画監督はフランスと行き来しながら、そこに何度も足を運ぶことになる。1940年の占領から逃れるため、そしてインドシナ時代の兵役から逃れるため。1977年、ついにジュネーブとローザンヌの間にあるロールに居を構えることになった。住民との接触を求めず、しかし、住民から逃げることもせず」とシンジック、つまりロールの市長であるモニーク・シュニャ=プグナルは振り返る。
ロール』では、ジャン=リュック・ゴダールは、スイス映画アカデミーの栄誉を拒否したように、街の栄誉も拒否した。時に人間嫌いになりそうなほどの慎重さ。アニエス・ヴァルダにドアを開けるのを拒否された時のようにね。監督には苦い思い出があることでしょう。ロールの町は、その最も輝かしい住人の一人である男については、なおさらである。当局は現在、ジャン=リュック・ゴダールの名を冠した広場の設置を検討しています。
ロルでは、映画の聖なる怪物は、群衆から逃れる隠者と地元のカフェで出会った退職者の中間のような、平凡な人生を送っていた。
ジュネーブでの通信簿、Jérémie Lanche